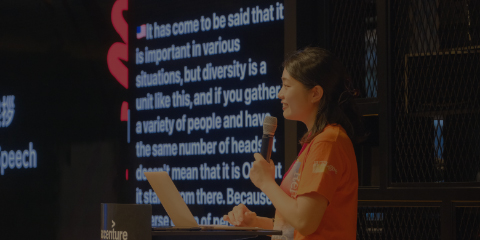#WELgee第二章 創業者・渡部カンコロンゴ 清花が語る十年間の険しい道のりと支え
WELgeeのはじまりは、2016年に当時学生であった渡部清花ら学生3人が偶然の出会いで集い、難民課題について話しはじめたことでした。そこから来年の2月で10年。活動初期からコロナ禍などいくつもの困難に直面しましたが、その度に多くの方に支えられて活動を継続してくる事ができました。
学生3人によるWELgeeの立ち上げ
Q:2016年、活動を始めたきっかけは何ですか?
当時、大学院の試験を受けた後で3月の合格発表まで時間がありました。実家でじっと待っているにもうずうずしてしまい、なにも計画がないまま2月に上京しました。その期間に出会い、参加したのが、認定NPO法人ETIC.主催の学生起業家育成プログラム「Makers University」。そこで出会った人たちとディスカッションを重ねる中で、テーマのひとつとして出てきたのが「日本の難民問題」でした。
特に難民、というトピックに関心を抱いたのには、当時向きあい続けていた問いがあります。
「国家が守らない/守れない人たちは、どのようにして生きていけるのか。」
大学時代に長期滞在したバングラデシュのチッタゴン丘陵地帯は、政府から先住民族への迫害や弾圧が長らく続き、中での人権侵害の情報も外に出にくい「隠れた紛争地域」でした。現地のNGO駐在員やUNDP(国連開発計画)のインターンを務めながら計2年滞在し、自分の国家にも内政には干渉できない国連にも人権が確保されない人たちがいること、その社会構造を目の当たりにしながら葛藤の日々を経験しました。

難民ーーー政府による迫害や弾圧、紛争や人権侵害から逃れてきた彼らは、チッタゴンで出会った彼らと同様に、「自分の国家に守られなかった人たち」でした。
その当時は、まずは彼らのことを知ろうと、アウトリーチの活動を行いました。その中で最初に訪ねたのが、私もよく知っていたチャクマ族の方。彼は約20年前に来日し、難民認定を得るまでに3度の難民申請を経験し、収容や不認定、数多くの弁護士とのやり取りを経て、迫害の恐れが認められ認定に至った経緯がありました。そこから少しずつ繋がりを広げ、徐々に多くの難民の方と出会っていきました。
まずは彼らと出会い話を聞こうと地域のお餅つきに一緒に参加をしたり、教会で行っていた難民の方々向けの日本語教室でボランティアで日本語を教えたり、収容された方々との面会のために入管に行くなどをしていました。
目の当たりにした、日々を生きるための必死な姿
Q:そうして出会ったインターナショナルズはどのような姿が印象的ですか?
昼間は支援団体の事務所を訪ね食糧をもらい、夜は24時間開いているマクドナルドで過ごしたり、冬は寒さをしのぐため150円のチケットを買って山手線に乗り続ける・・・そんな同世代たちがいる事に衝撃を受けました。彼らは身の危険からやっとこさ逃れてきたのに、日本で人生再建のとっかかりを得たいのに、ただ宙ぶらりんな法的地位で待っていた。
苦しい日々も教えてくれましたが、それぞれが、夢も持っていました。いつか平和になった国に戻って教育大臣になりたいとか、祖国の復興に携わりたいとか、日本でビジネスを成功させて母国とのブリッジになりたいとか。「宝の持ち腐れ感」を強く感じました。日本人の友人はほとんどおらず、難民認定の結果を待っている方も多くいらっしゃいました。カメルーンやコンゴ民主共和国、シリア等、母国の混乱が続く中、ネットを開く度に「友人が殺された」という知らせを受けている姿もありました。
ある日、「僕は地方出身だが、日本では東京しか見たことがない。日本の自然を見てみたいな。」と口にしたインターナショナルズがいたことがきっかけで、自身の出身地から近いこともあり、「富士登山をしよう!」ということになりました。いま振り返ると、持続可能性もない、思いつきのプロジェクトです(笑)

それでも、約35万円のクラウドファンディングを実施したところ、メンバーの知人や友人が支えてくれて達成しました。彼らの置かれた現状と、富士登山プロジェクトのことを新聞記事にしてくださった記者さんもいました。一方でその記事を受けて「そんな遊んでいる暇があったら国に帰れ」「難民を甘やかしていると日本の治安が悪くなる」というSNSでの反応もありました。そうか、このテーマは、一筋縄に応援者が増えるわけではなさそうだ、と初めて感じた瞬間でもありました。
ただ、その頃から今もずっと応援していただいている方々の存在が、これまでの私たちを支えてくださいました。本当にありがたく、心強く思っています。
仲間との模索と支えられてきた日々
Q:彼らの出会いから少しずつ事業を前に進めてきた事と思います。どのようにWELgeeのコミュニティ・エコシステムは広がってきたのでしょうか?
2017年頃から毎月「WELgeeサロン」を開催し始めました。WELgeeサロンは、毎回テーマを変えて日常の生活や自国の紹介、文化などの話題で集い、難民の方々と直接対話をする機会を設けました。第1回のサロンに参加してくれたのが、のちに現在の基幹事業である就労伴走事業の責任者・山本(元事業部全体総括、元理事)です。日本で「難民」に会ったことがある人なんてそうそういない。だからまずは彼らと出会い同じ目線で語り合い、友達になるという場を続けました。今回、代表のバトンをつないだ安齋や、いま育成事業部マネジャーを務める成田との出会いも、彼らが学生のときに参加してくれたWELgeeサロンでした。だんだんと、インターンの学生が工夫を重ねながらサロンの企画運営を担ってくれるようになりました。

Q:多角的に事業を展開していたひとつとして、どのようにキャリア事業を始めたのですか?
WELgeeサロンを重ねる中で、いつも盛り上がる話題のひとつが「キャリア」や「就労」「働くこと」でした。彼らは母国でなにかしらの役割を持っていた。これまで母国で培ってきた経験やこれから日本でやってみたい夢を語る彼らの熱意に触れる中で、緊急フェーズを乗り越えた人々が自立して働くこと、社会で活躍することに焦点をあてることがひとつの解決策になるかも、と仮説を持ちました。
「なぜ日本で働くのが難しいのか」「構造的な課題は何か」「法的な壁は何か」といった議論を、仲間たちと紐解いたり、今も顧問をしてくださっている行政書士の長岡由剛さんと在留資格の勉強会を重ねる中で、エンジニアになりたいというRさんと出会いました。彼は、母国では中国語とペルシャ語通訳士をしていましたが、エンジニア領域に関しては全くの未経験でした。ただ、トビタテ留学!JAPANの同期である起業家の友人に「エンジニアをゼロから育てながら事業を成長させたい」という方がいた縁で、Rさんをお引き合わせしました。彼はその後、厳しいトレーニングや試験に合格し、今では社長の右腕エンジニアとして大活躍しています。

Q:初期の頃に出会い、支えられてきた人にはどのような方がいますか?
この頃から応援いただいた方はたくさんいます。
創業期、成果が目に見える形では出ていないころから活動の理念に着目し、取り上げてくださったメディアさん・記者さんや、就労プログラムの要件定義やプログラム化までプロボノとして壁打ちいただいたコンサルの方、ひとりふたりと増えていき、今は700人にものぼるWELgeeファミリー(マンスリーサポーター)の皆さん、多くの方に支えられて、活動を継続・発展させることができました。
当時、住むところがないインターナショナルズたちと私たちメンバーもシェアハウスに暮らしていたのですが、「夏は暑すぎてあなたたち死んじゃうから、シェアハウスにクーラーを買って!」と30万円のご寄付をくださった方もいました(笑)。その方には、今でもプロボノ・寄付者として活動に参加いただいています。寄付者の方、ボランティアをしてくださった方、一人ひとりのサポートがWELgeeをつくってきました。
就労伴走事業の発芽
Q:そのような中で学生団体からNPO法人になったのには、どのような背景があったのでしょうか?
当時はまだ学生団体でしたが、就労伴走事業を構想していく中で、有料職業紹介業の認可取得が必要であり、それには法人化が必要であったこと、今後の活動を考える中で学生団体やボランティア団体としてではなく、メンバーがフルタイムで関わり、持続的に課題解決に向きあっていきたいといった思いもあり、法人化を決めました。2018年、NPO法人としてさらなる一歩をスタートさせました。
法人化した半年後、大きな転機となったのが新グループ経営改革推進研究会(新G研)の勉強会ゲストに呼んでいただいたことでした。インターナショナルズや山本など当時のメンバーとともに、その勉強会で現状の課題や挑戦の話をする機会を得ました。ここに参加されていた社会人の方々との出会いはすごく大きなものでした。今回理事となってくださった白石 章二さんにも、ここの場に参加いただいていました。白石さんにはその後、ヤマハ発動機株式会社にて、2人の難民人材を採用いただくプロセスにご尽力いただきました。

現在、毎年寄付をいただいている三菱マテリアル株式会社の方との出会いもこの場でした。その後、子会社(2019年当時)でも、母国で電気技師をしていた方の採用に取り組んでいただきました。
未曾有のパンデミック、キャッシュアウト寸前の危機
Q:その後、世界的なパンデミックであるコロナウイルスの蔓延があったかと思います。当時のWElgeeはどのような状況でしたか?
2020年、コロナウイルスには、WELgeeも例外なく影響を受け、厳しい状況に直面しました。
コロナの影響で収入源は縮小し、自転車操業状態でキャッシュアウト寸前となりました。特にそれまで収益の柱であった「企業研修」がリモートワークへの移行や企業における研修予算打ち切りの影響をうけ激減し、難民人材採用というまだまだ新しい領域に挑戦する余力は企業さんにもほとんどありませんでした。一方でインターナショナルズは、日雇いや非正規雇用の仕事からの解雇や生活困窮に直面し相談が相次ぎ、SOSは増大していました。

そんな中でもどうにか事業を継続できたのは、その時期をどうにか乗り越えようと奮闘したメンバーの存在があってこそでした。またこの時期に、先ほどお話した新グループ経営改革推進研究会で出会ったひとりのWELgeeサポーターから、「WELgeeがこの時期に踏ん張ることが大事だから」と用途指定なしの1,000万円のご寄付をいただきました。まだまだ組織基盤も脆弱で、頑張ってはいるものの成果といった成果を出すには至っていない私たちを信じて託してくださったご寄付。コロナで対面で会えなかった頃。オンラインミーティングでそのご提案をくださったのですが、今もその瞬間を覚えています。言葉にならない感謝の気持ちです。
ウクライナ・アフガニスタン情勢と、拡大する「期待」
Q:それから今に至るまで、どのような変化がありましたか?
2021年10月のアフガニスタンにおけるタリバン復権や、2022年2月のロシア軍によるウクライナ侵攻によって、難民問題への社会的関心がこれまでにないほどに高まりました。ウクライナ避難民に関わる団体も急増し、戦争や避難民の様子は連日報道されていました。その影響で企業からの問い合わせも増えました。特定の国のニュースだけが取り上げられることには複雑な気持ちもあります。同じような状況に置かれているのに、法的安定性が不安定なまま留め置かれている人たちが大勢いたからです。ただ、WELgeeとしては、こうしてイシューに着目が集まる中で事業をさらに前に進めると同時に、ウクライナだけでなく、アフリカ諸国など他の国からも難民が日本に逃れてきていることを同時に発信し続けました。ウクライナ避難民向けにデジタルワークショップを開催したり、既存の就労プログラムを通じ、インターナショナルズの人生再建につながる後押しを継続しました。
WELgeeは立ち上げから10年間の間、掲げたビジョンとミッションを中心に、それをともに追いかけるチーム、インターナショナルズ、寄付者、企業の皆さまなどとともにある事で活動を続ける事が出来ました。取り巻く社会情勢はその時々で変化しつつもWITHの精神とともに、周囲のサポートに支えられてWELgeeは存在し続けることができました。
バトンを託す、これからのWELgee

Q:歩みを重ねる中で、なぜ今回バトンを次に託す事にしたのでしょうか?
2020年のコロナの時期にわたしも立ち止まる機会があり、どう歩んでいくのか自身とも対話を重ねてきました。立ち上げた人が、その後もずっと代表であり続けることだけが、必ずしも正解とは限らないのかもしれない、といい意味で思う瞬間もありました。この間、思考の壁打ちをしてくださったメンターやコーチも、感謝を伝えたいかけがえのない存在です。今回のトランジションにおいて、メンバーとも濃い対話の時間を重ねる中で、「辞めるなんて無責任だ」なんて、きっと他の誰かには決してかけないような言葉を、気づかないうちに自分自身にはかける場面があったことにも、気がつきました。このメンバーならきっと次にバトンを託すことができる、もっと飛躍できるという信頼や心強さがこの選択肢を選ぶ背景にありました。
Q:これからのWELgeeに期待していることはありますか。
社会的なミッション、期待を寄せてくれる方々の声、インターナショナルズの存在など大事なものがWELgeeで活動する日々にはあると思います。だからこそ同時に、メンバーのそれぞれが、自分と対話する時間を持ち、自分の中にある自分らしさが発揮されているか見つめ続けてもらえたら。それが重なったWELgeeはより強く優しい組織であれると思います。
難民をめぐる課題は複雑性が高く、国際的にも未だに完璧な解決策があるわけではありません。現場が見えているからこそ、どうしてももどかしさが山盛りのときもあるかもしれないけれど、できないことばかりに目を向けるのではなく、自分たちの立場や役割だからできること・できてきたことに立ち返ってほしいです。
これまでの10年間がそうだったようにこれからもWELgeeだからこそできることがあると思います。クリエイティブにシャープに尖って、自分たちだからこそできる事へのチャレンジを続けてほしいです。
そして、これからも続くWELgeeの試行錯誤を、応援してくださる皆さんには、あたたかく見守っていただきながら、ぜひ引き続き声を届けていただけたら嬉しいです。皆さんの声と応援が、これからのWELgeeをつなぎ、支えていくと信じています。