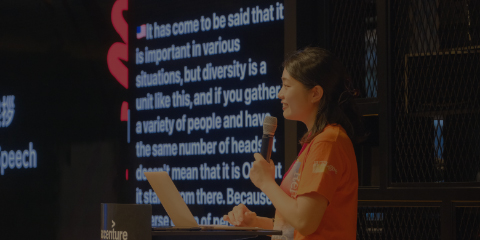#WELgee第二章 WELgeeを離れるふたりと、これからを担うふたり──WELgeeという“物語”を紡ぎ続けるクロストーク前編
WELgeeの立ち上げ期、そしてその後の存続危機をも乗り越えながら、団体の中心で尽力してきた山本菜奈と渡辺早希。そんな二人が、このたび「第二章」への移行に伴い、理事を退任する運びとなりました。
創業期を支えた2人の挑戦
WELgeeに入ったきっかけを教えてください。
山本:私は、大学入学当初から社会的マイノリティのエンパワーメントや、社会の産業やコミュニティの活性化にもつながる形での就労支援に関心を抱いていました。そのなかで、WELgeeサロンVol.1に参加したのが、WELgeeとの最初の出会いです。難民の若者たちと交流する中で、彼らが日本社会でその経験や想いを活かせる可能性を直感し、自分がやりたいことと重なることを感じて参画を決意しました。
渡辺:私は大学1年の時に難民に出会い、その後、韓国に逃れたイエメン難民の調査をしていました。彼らに年を跨いで会った時に、少し前向きに変化していたその背景には、コミュニティのサポートがあったことに気が付きました。その経験から、日本でも同様の取り組みをしたいと考えるようになり、まずは先例がないかと調べたところ、WELgeeにたどり着きました。その後、サロン事業のインターンとして参加することにしました。
お二人はこれまでどのような役割をWELgeeで担ってきましたか?
山本:現在の主軸事業である就労伴走事業の立ち上げを行いました。難民認定申請者が企業での雇用を通じて法的地位を安定化させるスキームを行政書士や弁護士の先生たちと確立させてきました。
就労伴走事業の立ち上げのきっかけは、難民の若者たちの「母国で学んできたことや積んできた経験を日本社会でも活かしたい」、「一度は逃れざるをえなかったけれど、母国の社会課題に新しい変化を生み出せる人になりたい」といった願いに触れたことです。難民になった自分たちにはその願いを実現できる道筋がないんだ、と聞き、そんな彼らと日本社会の架け橋をつくりたいと考えるようになりました。

また、WELgeeサロンに参加した直後から、北海道下川町という持続可能な森林経営やまちづくりで知られる町で産業振興の長期インターンをしたのですが、そこで目にしたのは、日本の少子高齢化と担い手不足の最前線で、会社や産業の未来を担っていけるような人材が不足している状況でした。日本にやってきた難民が日本社会で活躍する仕掛けができれば、日本の企業や産業、地域にとってもためになる、そんな互恵的な関係性が、多様性に寛容な日本社会を形づくるんじゃないかと考えました。
そこから育成/就労/共創事業/法人連携部を順次立ち上げ、統括する事業責任者として、戦略、人材採用や育成、チームマネジメント、広報・ブランディングに広く携わってきました。2022年には正式に理事になり、安齋の転職後の経営業務も渡部、渡辺らと担うようになりました。
渡辺:2020年4月にリソース部門統括として入社してから今に至るまで、事業の拡大を支えるための組織基盤強化や資金調達等を担ってきました。
インターンとしてかかわっていた頃のWELgeeは、事業拡大のタイミングにありました。しかし、学生団体からNPO法人になったばかり。やりたいことや理想は広がる一方で、会社組織としての基盤に関しては整備されておらず、毎日遅くまで頑張っているけれど、福利厚生もなく、給料もとても低い状況でした。
同時期、学生時代から参画していた別のワーキンググループでも、ソーシャルセクターで働く人の待遇や労働環境を改善しないと、優秀な若者が参画せず、そのうち業界全体が縮小してしまうのではないかということが課題として話されていました。
想いを持った人たちが取り組みを続けられるために、職員の待遇改善や組織の制度設計をしていく必要がある。それなら、参画したばかりの目の前の組織からまずはやってみよう。その想いから始まり、人事労務・会計財務・制度設計など、団体の持続可能性を支える基盤づくりに注力してきました。
これまでどんな苦労を乗り越えてきましたか?
山本:最も大きな苦労のひとつは、新型コロナウイルスの影響で企業の採用が一斉に停止し、WELgeeの対面活動や財政ポートフォリオそのものが機能不全に陥ったことです。4年間の実証事業を経て難民人材採用コーディネーションサービスJobCopass(現WELgee Talents)をリリースした矢先、これまで収益の柱であった研修事業もストップし、バーンアウトするメンバーも出て、キャッシュアウトが目前に迫るという状況に、しばらく謎の胃痛と不眠が続きました(笑)
渡辺:団体が事業停止と財政難に直面したコロナ禍は本当に苦労した時期でした。入社して一年足らずの時期に、団体はキャッシュアウト寸前という状況の中で、助成金申請や融資交渉に奔走。まさに「この船を沈めてはならない」という一心で、体力と気力を振り絞って組織の存続に取り組みました。

危機的状況を乗り越えた後、次は「この先の10年、20年を見据えた持続可能な組織づくり」という課題が立ちはだかりました。少しずつ実績を積み重ねてきた中で、組織としての信頼が社会から問われるようになります。対外的な注目が集まる一方、内部では仮説検証の連続。外からの見え方と内とのギャップが大きくなっていく中で、学生団体の延長から卒業し、より法人として成長していくにはどうすればいいのか。その問いを持ち続けながら、団体の中長期的な基盤づくりに尽力しました。
これまでの印象的な挑戦や決断にはどのようなものがありますか?
山本:印象に残っている決断は、2021年頃に作成した、中長期プランについてです。
もともと2019年くらいまでは「難民認定が厳しい日本で、就労を通じた難民認定申請者の在留資格変更が社会的・法的なブレイクスルーになる」仮説の実証を重要な目標に置きつつ、自分自身も住んでいたシェアハウス事業や企業研修、プログラミングスキル研修、交流事業など多角的な事業運営をしていました。
2019年に前述の仮説が実証できて、2020年にサービスをリリース。その後、1年ぐらいはコロナ禍で生き残ることだけで必死でしたが、それが落ち着いたころに、次に目指す目標が不明確な状態であることに気が付きました。そこで社会的インパクト創出の中長期的なプランを、事業を間近で見てきた自分が素案づくりをして、当時の経営・マネージャー陣と議論をしていきました。
難民問題というのは外部環境による対象者の数や属性の変化、法制度の変化を読みきれない部分も多いです。難民人材の活躍が社会に浸透しはじめているといえる状態に指標を置くとしたら、何が明確でシンプルかということを議論し、2025年度まで難民人材雇用企業100社の事例を生み出すという定量的な目標や、定性的なマイルストーン、例えば地域の中小企業さんでの採用、家族の呼び寄せの実現、難民就労を後押しする企業陣のプラットフォーム立ち上げといった目指すアウトカムを設定しました。
振り返ると手弁当で大まかな計画でしたが、WELgeeならではの社会的インパクトを追求するためにはどういうチーム編成が必要なのか、何をしないのかということを、シャープに議論していくことになりました。
渡辺:ずっと決断の連続だったような気がします。ただ、自分にとって印象的だった決断は、「自分は事業から離れて、バックオフィスに専念する」と決めたことです。この時の決断が、今回の理事退任にも繋がっていく一つの分岐点だったとも言えるかもしれません。
もともとインターナショナルズとの直接的な関わりも好きで、インターナショナルズとのリレーション構築部分のマネジメントも兼任していました。しかし、組織の成長を加速させていくには、自身のリソースをリソース部門の役割に注力させたほうが良いと判断しました。このタイミングで、組織に必要な機能やそれぞれの役割も整理しつつ、その道を選びました。
ふたりの参画からこれまでの歩み
そんななかで、加藤と成田のお二人が参画されました。
山本:いまJasmine(成田)がリードしてくれている育成事業は、人材と企業の採用をコーディネートするキャリアコーディネーターやフルタイム職員が時間をかけてインターナショナルズに伴走していた仕組みを、よりスケールさせて多くの人に届けるため、自分たちで行う以外のなんらかの方法を取れないか、という問いの中で生まれました。社会人プロボノさんが就職や転職、採用や育成の経験を活かして、インターナショナルズのよき友人でありメンターとして直接伴走するモデルへと拡張を行いました。 弁護士や支援団体の職員、社会福祉の専門員でない一般の人たちも、難民の人たちと日本社会の架け橋になれることがWELgeeのビジョンにもマッチする、と考えての挑戦でした。
成田:2023年3月、育成事業部に参画しました。2024年4月にはマネージャーに就任し、育成事業の拡大と質向上を担ってきました。メンターシッププログラムなどをNanaさん(山本)から引き継ぎながら、より多くの人たちを巻き込み、関係人口を増やすための、システムや基盤作りに取り組んできました。
今は、スタッフとともに、WELgeeと接点を持つインターナショナルズを増やし、メンターシップの数を増やし、それによって自立して就職活動できるインターナショナルズを増やすことに取り組んでいます。
加藤:私は、2022年10月にPR部のインターンとして参画し、SNSの運用等をしていました。2023年3月、職員になるお誘いをいただいたタイミングで、WELgeeファミリー(継続寄付者)の拡大を任され、WELgeeファミリーの新規獲得に主軸を置いて活動してきました。それに合わせて、PRの仕事も続け、取材・登壇の調整や、メディア向けの勉強会の企画運営を行いました。
去年の11月にPRマネージャーになってからは、ファンドレイジングの仕事も引き続き続けながらも、PRの仕事の分量を増やし、戦略策定、インターンのマネジメントから、現場のひとつひとつまですべて行っています。PRというのはパブリックリレーション(対外の関わり)の略なので、経営課題を見ながら、必要なリレーション調達や対外コミュニケーションに関わることは全般的に柔軟に行うよう意識しています。
.jpg)
これまで苦労したことややりがいを教えてください。
成田:私はWELgeeのカルチャー、働き方に最初は苦労してたと思います。全然アジェンダ決めてないで、ミーティングが始まることもあり(笑)前職の経験があったからこそ、モヤモヤ感がすごくあったこともありました。
加藤:正直、ずっと苦労の連続です。私は新卒で、社会人経験がない状態で入っていることもあり、どの役割についても、圧倒的に力不足であり続けてるなと、少なくとも自分の評価としては思い続けています。自分自身は何も材料を持ってない状態なのに、何かを任される、といったことがすごく多かったので、それをどう扱えばインパクトを創出していけるのか、というのは、自分の中に経験や定まった型がなかったからこそ、特に苦労してきました。いまも、まだまだ苦労と挑戦の連続です。
ただ、その一方で、自分に伸びしろがあるんだと根拠なく信じて、目の前の課題に向き合っていくプロセスを経ると、気がついたら本当に力が伸びて、生み出せるインパクトが増えている。自身の成長を感じられることや、それによって組織や社会に与えられる影響が増えていることに、すごくやりがいを感じています。
成田:私にとって、やりがいは年々変わってきています。入職当初は初回面談で、新しい人に出会えて、その人のポテンシャルを見つけられることにやりがいを感じてました。
今のやりがいは、難民の課題を知らなかった人たちが、課題に触れて、プロボノとして、インターナショナルズ1人1人に触れて、それが彼らの人生も変える経験になること。彼らの存在が、社会がポジティブになるかもという兆しをくれる気がします。
後編につづく