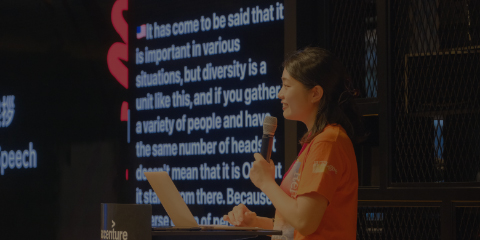#WELgee第二章 WELgeeを離れるふたりと、これからを担うふたり──WELgeeという“物語”を紡ぎ続けるクロストーク後編
WELgeeの立ち上げ期、そして存続の危機をも乗り越えながら、団体の中心で尽力してきた山本菜奈と渡辺早希。そんな二人が、このたび「第二章」への移行に伴い、理事を退任する運びとなりました。
今回の記事では、二人の後輩であり、現在はそれぞれ育成事業部マネージャーとPR部マネージャーとしてWELgeeの次のステージを担う、成田茉央と加藤冬華を迎え、四人による対談をお届けします。
今回は後編として、この1年の四人にとってのトランジションのプロセス、今後それぞれが描いていく未来についてお届けします。
トランジション - 退任を決断した理由とトランジションのプロセス
退任を決断した理由を教えてください。
渡辺:2022年に理事に就任したときから、「WELgeeがある程度拡大して、次のステージに進める状態にできたら、そのタイミングで自分自身のキャリアのステップも次の一歩に進もう」とぼんやりと決めていました。だから、今回の退任も「そろそろ、その時がきたかな」という気持ちに近いです。
ただ、それを決定づけた出来事があるとすれば、昨年の世界難民の日のイベントでした。すごく意味のある場でしたし、協力いただいた皆さまには感謝が尽きません。一方で、参加してくださる企業やインターナショナルズの顔ぶれが一昨年と変わっていない現状を目の当たりにし、「このまま同じメンバーで同じアプローチを続けていても、大きな変化は生み出せないんじゃないか」と思ったんです。さらなる飛躍のためには、これまでとは異なる視点を取り入れて、中長期で社会にどんな影響を与えたいかを考えて行動できる組織になる必要がある。
それと同時に、自分自身のキャリアを考えた時にも、難民の日本社会での活躍を後押しするうえで、何がまだ足りていないピースなのかをもう少し違う角度から探していきたい。そう感じて、7月の理事会で退任の意向を正式に表明しました。
山本:コロナ禍での活動存続の危機のころから、たとえ最後の1人になってもWELgeeを守る、というラストマンシップが自分の中にありました。
ですが、2023年に産休・育休でWELgeeに入って初めて現場から離れたことをきっかけに、WELgeeのビジョンや価値観を体現しながら事業を前に進めてくれるチーム、頼もしいメンバーが今のWELgeeにいることを実感しました。

そんな中で、挑戦したくなったことがありました。
WELgeeに関わりはじめたきっかけが「ここにポテンシャルがあるのに、なぜ点と点がつながっていないんだろう?」というもどかしさだったのですが、それを再び強く感じたのが、コロナ禍で国境が閉ざされた時期、海外からたくさんの問い合わせが届いたことです。パキスタンにいるアフガニスタン難民の方から英語で連絡がきたり、コンゴ民主共和国から「WELgeeのプログラムに参加したい」とメッセージが届いたり。そのたびに、世界はこんなにもつながっているんだという実感と同時に、WELgeeのプログラムが日本に何らかの方法で辿り着いた難民の人たちのみを対象としていることに対するもどかしさを感じてきました。同時に、企業と対話をすると「やる気をもって長期目線で働いてくれる人材が足りない」と言う声が業種や職種問わず多く、この両者がもっとボーダーレスに出逢えたらいいのにという想いが、どんどん強くなっていきました。
それならもう一度、点と点をつなげていく作業を、自分自身の手でやってみたい。たくましく育ったWELgeeを見守りつつ、新たな可能性を繋げる挑戦をしたいなと思って、理事を卒業する決断をしました。

今回残ることに決めた二人が退任について聞いたときは、どのように感じましたか?
成田:私は、お二人が退任されるだろうということをなんとなく察知していましたし、前職の経験もあり、組織が変わっていくのは当然のことである、と変化自体は受け入れていました。ただ不思議なことに、代表も含め多くの創業メンバーが辞めていく中でも自分が辞めるという選択肢はなく、合宿の際には「次期代表に立候補する人がいなければ自分がやる」と宣言したほどです。WELgeeを守らなければ、続けなければ、といった強い気持ちがありました。
そののち、約1年間、次期体制構築に向けての濃い議論と、自分とWELgeeと向き合う時間がありました。WELgeeをどうしていくのかという話にあわせて、それに向き合う「自分」はどうありたいのかと向き合い、持続的なインパクトが出せるように、「自分」と「WELgee」の心地よい関係性も考えるようになりました。

加藤:おふたりの退任を聞いた合宿の帰途、Jasmine(成田)と1時間ほど代々木から渋谷までお散歩しました。その際に、Jasmineとお話をするなかで、「何がなんでもWELgeeに残り続けよう」と意思が自分の中で固まりました。移民や難民に向き合うことがライフミッションであること、この団体が好きであること、創業メンバーたちを心から尊敬していることから、引き継がれてきたものを自分がしっかり受け取り、WELgeeを守り、拡大していこうと決めたんです。
だからこそ、退任をお聞きしてからは、組織として納得のいく決断、第二章のはじまりを迎えるために自分がどう動くべきか、常に考え続けました。特にマネージャーになったことや、共同代表の選択肢を提示されたことで、視座が上がり、組織や社会と一段と深く向きあうきっかけになりました。これからもWELgeeに対する強い愛を軸に、創業メンバーが積み上げてきてくださったものを大切にしつつ、より一層変わりゆく社会に大きなインパクトを残し、社会構造にメスを入れていきたいと思ってます。

バトンを渡したふたりにとって、このトランジションのプロセスはどのような時間だったのでしょうか?
渡辺:言葉にするのが難しいほど濃い時間でした。卒業の意向を表明したものの、ここまで築いてきた組織基盤をまた振り出しに戻すことはしたくなかった。だからこそ、トランジションのプロセスは次世代を担うメンバーのオーナーシップを引き出しつつ進めながらも、自分や創業メンバーが抜ける穴はHRに責任を持つ自分が埋めなければいけない。そう腹を括り、現場にいるメンバーがこれからも安心してWELgeeを成長させていけるように、組織全体のリクルーティングをしつつ、「マネージャー」の役割を任せ、現場のメンバーにも視座を少しずつ引き上げてもらったりなど、人材育成を意識して動きました。
振り返ってみるとこの1年は、退任を見据えながらも、日々の議論や意思決定に全力で関わり続ける、バランス感覚が常に求められた期間でした。しかし、だからこそ、自分も人間としてすごく成長できたな、と感じています。
山本:自分自身が卒業を決意したところから、Saki(渡辺)の卒業のタイミングと重なったこともあり、今後の組織のかたちを大きく問う必要がでてきました。そんな時にオーストラリアで開催された太平洋地域の非営利団体のリーダーが集まる研修で、「サクセッションプランニング(Succession planning)= 後継者育成」や「事業承継」といったトピックが参加者によって、オープンかつプロフェッショナルに話し合われている場に身を置き「これは経営者として避けて通れない重要アジェンダなんだ」とスイッチが入りました。
中核を担っていたメンバーが卒業するタイミングで、どう進んでいくかという議論は決して前向きな内容ばかりではありません。心が折れそうなときも、いろんな人の応援や親身な協力によって、その先にそれぞれにとって前向きな第二創業期があると信じることができ、進んでこれました。
「議論し尽くしたよね、検討し尽くしたよね、もうこれ以上ないよね」というところまで議論を重ねてきたみんなをすごく敬意しますし、こうやってトランジションしたWELgeeは、今後どんなことがあっても乗り越えていけるレジリエンスがついたと思います。

今回の退任は一緒に働いてきたふたりを含む、バトンを託せる仲間の存在が大きかったと思います。加藤や成田はどんな存在ですか?
渡辺:Jasmine(成田)とまりりん(加藤)は、”一言えば十わかってくれる”タイプの人たちで、最初からWELgee特有のハイコンテクストな文化に頑張って適応してくれていたのが印象的でした。WELgeeはあまりマイクロマネジメントをしないし、自分で今何をしなきゃいけないか考えて動くことが求められる。そんな中で、組織に今何が必要かを、指示したり、伝えたもの以上に打ち返してくる。
私たちにも正解がわからない問いを一緒に模索してきたからこそ、最初から対等なスタンスで向き合えていたなと思います。特にここ1年もすごい濃い関わりをしてくれてきた信頼できる存在です。二人とも違う良さがあるけれど、どちらもWELgeeに必要な存在で、「この人たちがいれば大丈夫だ」と心から思わせてくれる。言葉のセンスも良くて、語録をよく生むし、日本語の先生になった気分になることもあるのですが。(笑)
山本:2人を見ると「後任者」という感じではなく、『BORUTO』、少年漫画『NARUTO』の次の世代の物語が始まる、あの感じが思い浮かびます。(笑)最初はなかなかに混沌としたWELgeeの活動と組織と世界観を、誰がどう引き継いでくれるか想像ができなかった。しかし、Jasmine(成田)がインターナショナルズとの関わりに対して熱くこだわりを持って話してくれたり、まりりん(加藤)が「WELgeeをこうしていきたい!」とすごい熱量で語ってくれたり。その姿を見たときに「”第二章”が始まるな」と心から思えたんです。
私はこれからのWELgeeを、「本編が早く見たいファン」のような気持ちで見守っています(笑)。新体制が思いっきり次のWELgeeの世界観や事業をつくっていったときに、彩り豊かな物語が新たに生まれてくるのかなと、期待しています。
#WELgee第二章 - これからも続く、それぞれの歩み
今後、WELgeeにとって大切にしてほしい価値や文化はなんですか?
渡辺:「クレド(理念)」に立ち返り続ける姿勢を大切にしてほしいです。何をいま為すべきかを常に自問し、クレドに立ち返り続ければ、たとえ再び困難が訪れてもきっと乗り越えられると信じています。クレドを共につくった安齋が新体制に再び加わる今、その精神は確実に受け継がれていくと期待しています。
山本:「自分自身を大切にすること」。WELgeeは熱意ある仲間が集う魅力的な場ですが、その熱意も魅力も、日々の生活の中で丁寧に耕されてこそ育つものだと考えています。忙しくても、自分と向き合う時間を持つこと。家族と過ごす時間とか、ちょっと旅して回ってみたりとか、一日中本読んでみたりとか。その余白こそが、インターナショナルズとともにいきいきと暮らす社会を実現するための基盤になると思っています。
加藤:自分は、自己犠牲をして頑張りすぎる気質ではあるのですが、休みたいときに適切に休むことができる、滝行に行きたいときに行ける、そんな環境をつくっていければと思っています。
今後はどのような進路を思い描いていますか?
山本:先ほど述べた「点と点が繋がっていない」というもどかしさに、もう一度向き合ってみたいと思っています。新たにNPOを立ち上げて、そうした“つながりきれていない可能性”をつないでいくような事業に挑戦したい。分断や不寛容がひろがる今の世の中で、国や立場の境界を超えて、人と人がともに働き、くらし、未来をつくっていける仕組みを築きたい。WELgee創業期からと変わらない想いを、今度は、また新たな形で実現したいと思っています。WELgeeともエコシステムの同志として、インパクトを広げていきたいです!
渡辺:正直なところ、次のキャリアのことは明確には決めておらず、とりあえず大好きなアラブに旅に出ようと思っています。WELgeeを離れることを決めた直後は、民間企業での就職活動をしていました。ただ、体制移行のプロセスを全力でやりながら、自分の就活は片手間でというのもなんか違うし、このままだと「五感を使って人生を楽しむ」という感覚をどこかに置き去りにしてしまいそうだなと思って。
人生100年時代、ちゃんと自分の感覚を取り戻す時間を持ってから、またその先を考えても遅くないのではという考えに至りました。次に何をするかは、体制移行のプロセスをやり終えた今の自分だからこそ見える景色があるし、旅をしながら本来の在り方を取り戻した次の自分が、きっと見つけてくれるだろうなと思っています。

新体制の中で今後どんな役割を果たしていきたいと思っていますか?
成田:トランジションのプロセスの中でひとつ、団体として早い段階で決めたことが【存続・拡大】を目指すということです。私自身も、できるだけ多くのインターナショナルズと出会い、彼らの人生再建に伴走していけたらと思っています。
ただ、やはり拡大し、前に進んでいくためにも、組織基盤・根幹作りが大切だと感じています。民間企業から転職してきたなかで、NPOには自己犠牲が強いられてしまう団体も多いことに気が付きました。幸せそうに働いている人もいるのですが、無理している方も多いなと感じています。どんな人でも活躍できる、NPOでもきちんとキャリアが歩める、そういった土壌を作れるような団体にWELgeeもなれればと思っており、組織や人材の育成、待遇水準の向上、評価基準の整備などにも取り組んでいければと思っています。
加藤:私は自分がこれをやりたいってのが良くも悪くもなくて、社会においてWELgeeが果たすべき役割があり、そこに資することで自分の特性が活きることがあったら何でもやろう、と思っているのが正直なところです。自分自身は特定の肩書を持っていることに居心地悪さを感じるくらい、自分のロールをあまり固定のものとして捉えていません。
組織にとって今大事なこと、必要なことをちゃんと見極めて、そこに尽力できるように、外部からのリソース調達ももちろん、知識や経験を得られる外部の機会も利用して自分自身の力もつけて、それを組織にとことん還元する、ということができれば、と思っています。
あと、良くも悪くも25歳、自分自身のことを「まだまだやれる若者」だと信じています。ポテンシャルと体力だけが取り柄だと思ってるので、それを存分に生かして、進んでいければとは思っています。
今後のWELgeeで描いている未来像があれば、ぜひ聞かせてください。
成田:難民支援に取り組む団体や個人間での、横での連携が進む未来を作りたいと強く思っています。実際に他団体や個人支援者の皆さんと議論をする中で、やっぱりスタンスの違いなど”難しさ”が存在するというのは感じました。ただ、協力して、それぞれ異なるスタンスを尊重しつつ、それぞれの強みやリソースを活かしてできることを行いつつ、補いつつ、インターナショナルズの幸せという一軸において、同じ方向を向いていけるといいなと考えています。そこにビジネスセクターも巻き込んで、社会全体として難民をポジティブに受け入れる社会が近づけたらいいなと考えております。
加藤:成田と同じく、組織開発は今のWELgeeが取り組んでいくべきことのひとつだと思っています。みんなが自分らしさを生かして、楽しく仕事に取り組めて、その化学反応が起きたときに、一番団体として成果が生まれてくると強く思っているので、その化学反応がおこるように、仕組み作りも含め、組織を整えていきたいとすごく思っています。
あとは積極的に難民課題に関わる企業をより一層増やしていきたいです。やはり企業の存在、その集合体である産業界の動きは、社会構造の中ですごく大きな影響力があります。彼らの要請が実際の制度を大きく変えることもあるのをみています。
WELgeeが創設してからの10年で、ウクライナ侵攻もあり、企業がこの課題に関わるハードル自体は低くなりましたが、まだまだそれでも難民課題には関わりにくいと感じている企業や未だ関心をもっていない、課題に出会えていない企業が多くいるのも事実です。そこを突破し、前向きに関わる企業を着実に増やしていくこと、同時に産業界に対して面でアプローチをかけていくことにも力を入れたいと思っています。

WELgeeとの出会いをきっかけに難民課題に関心を持ち、彼らの状況によりそい、それぞれの得意なやり方でかかわる企業が増えることが、より彩り豊かな社会につながっていくと考えています。
企業とのリレーションはWELgeeにとって財産です。それを大切に、より広い視野を持ってアプローチしていければと考えています。